



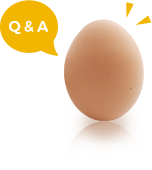
卵は毎日の食卓の中で、ありとあらゆる料理に活用されていますが、その卵について案外知らないことが多いものですよね?
皆様からもお電話やお葉書などで、かなりのご質問をいただきました。それらのご質問の中から皆様が日頃不思議に思っていたり、
質問が多かったものをお答えしていこうと思います。みなさんの毎日の卵料理にご活用していただけると思います。
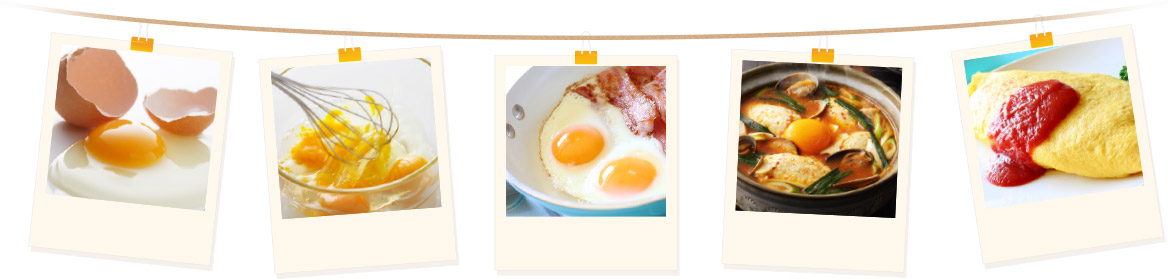
 産み立ての新鮮の卵は、殻の表面部分がザラザラとしています。これはクチクラと言われる膜が覆われているためです。
産み立ての新鮮の卵は、殻の表面部分がザラザラとしています。これはクチクラと言われる膜が覆われているためです。 購入してから室温(15℃)で保存した場合、3週間ぐらいは大丈夫です。しかし、もちろん卵は生ものですから、時間がたてば次第に鮮度は落ちていきます。冷蔵庫(5℃)に入れればさらに長持ちします。
購入してから室温(15℃)で保存した場合、3週間ぐらいは大丈夫です。しかし、もちろん卵は生ものですから、時間がたてば次第に鮮度は落ちていきます。冷蔵庫(5℃)に入れればさらに長持ちします。
 卵はよく見ると尖っている方と、丸い方があります。冷蔵庫の卵ポケットにしまう場合丸い方を上にして保存しましょう。卵の丸い方には気室があり、そこは細菌が繁殖しやすいのでそこから卵黄部を近づけない様にするのと同時に、丸い方を上にすることで卵黄が中心にきて安定するために長持ちするのです。
卵はよく見ると尖っている方と、丸い方があります。冷蔵庫の卵ポケットにしまう場合丸い方を上にして保存しましょう。卵の丸い方には気室があり、そこは細菌が繁殖しやすいのでそこから卵黄部を近づけない様にするのと同時に、丸い方を上にすることで卵黄が中心にきて安定するために長持ちするのです。 卵を割ると必ず、黄身部分に白いひも状のものが付いていますが、これは「カラザ」と呼ばれるものです。「カラザ」は卵黄を卵の真ん中につり下げるハンモックの役目をしています。ですから卵の尖った方に1本と丸い方に2本ねじれて付いていて卵黄をしっかり守っていいるのです。
卵を割ると必ず、黄身部分に白いひも状のものが付いていますが、これは「カラザ」と呼ばれるものです。「カラザ」は卵黄を卵の真ん中につり下げるハンモックの役目をしています。ですから卵の尖った方に1本と丸い方に2本ねじれて付いていて卵黄をしっかり守っていいるのです。 ちょっと気持ちが悪いのですが・・・と良くあるご質問です。この血斑は鶏の病気や特殊原料の給餌によってのものではなく、全くの正常な鶏が産む卵で見られる現象なのです。
ちょっと気持ちが悪いのですが・・・と良くあるご質問です。この血斑は鶏の病気や特殊原料の給餌によってのものではなく、全くの正常な鶏が産む卵で見られる現象なのです。 卵を割ったときに2つとか3つ黄身が入っていてびっくりする事があります。これは人間にも双子、三つ子とあるように不思議な事ではありません。これは2個又は3個の成熟した卵胞(卵黄)が同時に排卵されたり、先に排卵された卵胞がまだ、鶏の卵管の上部にある時に、再び排卵され、複数の卵胞が輸卵管を通っていく時に、卵白分泌部から分泌された卵白に包まれてしまい、そのまま一つの卵殻で産卵されたものなのです。
卵を割ったときに2つとか3つ黄身が入っていてびっくりする事があります。これは人間にも双子、三つ子とあるように不思議な事ではありません。これは2個又は3個の成熟した卵胞(卵黄)が同時に排卵されたり、先に排卵された卵胞がまだ、鶏の卵管の上部にある時に、再び排卵され、複数の卵胞が輸卵管を通っていく時に、卵白分泌部から分泌された卵白に包まれてしまい、そのまま一つの卵殻で産卵されたものなのです。 卵の重量によって、農林水産省が定めた選別するための取引規格です。卵の価格決定や私たちが卵を買う時の選別の基準を目的としています。L玉は重量64~70g未満M玉は58~64gというように定められていますが、実際は卵の重量に関わらず、卵黄の大きさはほとんど同じなのです。ですから大きな卵は卵白が多く、小さいものは少ないということなので、料理や好みに合わせて購入しましょう。
卵の重量によって、農林水産省が定めた選別するための取引規格です。卵の価格決定や私たちが卵を買う時の選別の基準を目的としています。L玉は重量64~70g未満M玉は58~64gというように定められていますが、実際は卵の重量に関わらず、卵黄の大きさはほとんど同じなのです。ですから大きな卵は卵白が多く、小さいものは少ないということなので、料理や好みに合わせて購入しましょう。
 スーパーで売られているそのほとんどが無精卵です。鶏は交尾をしなくても25時間に1個の割合で卵を産んでいくのです。交尾をして産まれたものは「有精卵」となります。卵を次々と産んでいくメカニズムはメスの鶏の排卵のようなものなのです。
スーパーで売られているそのほとんどが無精卵です。鶏は交尾をしなくても25時間に1個の割合で卵を産んでいくのです。交尾をして産まれたものは「有精卵」となります。卵を次々と産んでいくメカニズムはメスの鶏の排卵のようなものなのです。
 卵には7,000から17,000個も小さな穴(気孔)があり、酸素を取り入れています。それは、卵黄の表面にある1~2mmの白い小さな丸い部分が卵の胚なのですが、卵内部で発生した炭酸ガスを排出しています。そして胚はその呼吸に必要な酸素を取り入れ、ガス交換をしているのです。このことを卵が呼吸しているというように呼んでいます。
卵には7,000から17,000個も小さな穴(気孔)があり、酸素を取り入れています。それは、卵黄の表面にある1~2mmの白い小さな丸い部分が卵の胚なのですが、卵内部で発生した炭酸ガスを排出しています。そして胚はその呼吸に必要な酸素を取り入れ、ガス交換をしているのです。このことを卵が呼吸しているというように呼んでいます。
 カラ(卵殻)と、クチクラ(殻の表面を覆っているザラザラした膜層)には、先にも述べたように「プロトポルフィン」という蛍光色素が含まれていますが、この含有量によって卵の殻の色が違ってきます。鶏の色素(鶏の品種)の沈着量により、決まるので、茶色の鶏の多くは赤玉を産卵することになります。しかしながら鶏の羽の色とは実は無関係なので、茶色い羽の鶏でも白玉を産む鶏もあるのです。卵の殻の色は鶏の持つ「プロトポルフィン」に決定づけされます。
カラ(卵殻)と、クチクラ(殻の表面を覆っているザラザラした膜層)には、先にも述べたように「プロトポルフィン」という蛍光色素が含まれていますが、この含有量によって卵の殻の色が違ってきます。鶏の色素(鶏の品種)の沈着量により、決まるので、茶色の鶏の多くは赤玉を産卵することになります。しかしながら鶏の羽の色とは実は無関係なので、茶色い羽の鶏でも白玉を産む鶏もあるのです。卵の殻の色は鶏の持つ「プロトポルフィン」に決定づけされます。
 卵の特性は大きく分けて3つあります!卵料理や加工品はその3つの特性を利用して作られているのです。これを「三大特性」と言っていますが、それは、「凝固性」と「気泡性」と「乳化性」です。
卵の特性は大きく分けて3つあります!卵料理や加工品はその3つの特性を利用して作られているのです。これを「三大特性」と言っていますが、それは、「凝固性」と「気泡性」と「乳化性」です。 ゆで卵を上手につくる基本は5つあります。
ゆで卵を上手につくる基本は5つあります。 実はこのうすく白い色に濁っているのは、新鮮な産み立ての卵の大きな証拠でもあります!
実はこのうすく白い色に濁っているのは、新鮮な産み立ての卵の大きな証拠でもあります! 産卵の時の汚れなどが消費者が嫌がることが多いために、現在の卵はそのほとんどが洗卵機などで洗ってから出荷しています。それでも汚れを気にして洗う方がいますが、全くその必要はないのです。
産卵の時の汚れなどが消費者が嫌がることが多いために、現在の卵はそのほとんどが洗卵機などで洗ってから出荷しています。それでも汚れを気にして洗う方がいますが、全くその必要はないのです。 現在は卵の賞味期限表示は食品衛生法により義務づけられていますので、表示のない卵はありません。その賞味期間とは「生」(なま)で食べられる期間の事です。ですから賞味期間を多少過ぎていても、加熱処理したものであれば充分食べることができます。
現在は卵の賞味期限表示は食品衛生法により義務づけられていますので、表示のない卵はありません。その賞味期間とは「生」(なま)で食べられる期間の事です。ですから賞味期間を多少過ぎていても、加熱処理したものであれば充分食べることができます。 何となく不思議に思うかもしれませんが生卵の方が断然日持ちします。それは生卵は生きているからなのです!人間が呼吸しているように、卵は卵殻(殻部分)には、気孔があり、これは7,000~17,000個もの小さな穴が開いています。この気孔で卵の胚の呼吸(卵黄の表面にある1~2mm程度の白い小さな丸い部分)に必要な酸素を随時取り入れているのです。そして内部で発生した炭酸ガスを排泄し、いわゆる呼吸である「ガス交換」が行われているのです。これに比べゆで卵や味付け卵は5日~7日程度ですし、これ以降過ぎたものを食べるのはよくありません。
何となく不思議に思うかもしれませんが生卵の方が断然日持ちします。それは生卵は生きているからなのです!人間が呼吸しているように、卵は卵殻(殻部分)には、気孔があり、これは7,000~17,000個もの小さな穴が開いています。この気孔で卵の胚の呼吸(卵黄の表面にある1~2mm程度の白い小さな丸い部分)に必要な酸素を随時取り入れているのです。そして内部で発生した炭酸ガスを排泄し、いわゆる呼吸である「ガス交換」が行われているのです。これに比べゆで卵や味付け卵は5日~7日程度ですし、これ以降過ぎたものを食べるのはよくありません。
 有精卵も無精卵も味や栄養に違いはありません。味や栄養価は飼料が影響します。
有精卵も無精卵も味や栄養に違いはありません。味や栄養価は飼料が影響します。| 区分 | ラベル色 | 基準 |
|---|---|---|
| LL | 赤 | パック中の鶏卵1個の重量が70g以上、76g未満であるもの |
| L | オレンジ | パック中の鶏卵1個の重量が64g以上、70g未満であるもの |
| M | 緑 | パック中の鶏卵1個の重量が58g以上、64g未満であるもの |
| MS | 青 | パック中の鶏卵1個の重量が52g以上、58g未満であるもの |
| S | 紫 | パック中の鶏卵1個の重量が46g以上、52g未満であるもの |
| SS | 茶色 | パック中の鶏卵1個の重量が40g以上、46g未満であるもの |
 そういえば鶏は朝卵が産まれることは当たり前のようになっていますが、夜には産まないのはなぜなのでしょう。それは、鶏の産卵には、光(光線)が大きな役割を果たしています。
そういえば鶏は朝卵が産まれることは当たり前のようになっていますが、夜には産まないのはなぜなのでしょう。それは、鶏の産卵には、光(光線)が大きな役割を果たしています。 先にも述べたように鶏は交尾をしなくても約25時間に1個ずつ卵を産んでいくのですが、もし、交尾していれば「有精卵」でそのまま育てれば、ヒヨコが産まれますし、交尾なく産まれる卵は「無精卵」となります。スーパーなどで販売されているものはそのほとんどが「無精卵」となります。この無精卵を産む鶏は交尾なく一羽ずつ「ケージ」といわれる仕切られたカゴのようなもので飼われ、毎日無精卵を産んでいるわけです。その交尾なくして産まれる無精卵は、人間でいえば排卵のようなものと考えれば、判りやすいでしょうか。
先にも述べたように鶏は交尾をしなくても約25時間に1個ずつ卵を産んでいくのですが、もし、交尾していれば「有精卵」でそのまま育てれば、ヒヨコが産まれますし、交尾なく産まれる卵は「無精卵」となります。スーパーなどで販売されているものはそのほとんどが「無精卵」となります。この無精卵を産む鶏は交尾なく一羽ずつ「ケージ」といわれる仕切られたカゴのようなもので飼われ、毎日無精卵を産んでいるわけです。その交尾なくして産まれる無精卵は、人間でいえば排卵のようなものと考えれば、判りやすいでしょうか。
 黄身の色が黄色い濃い色だととても美味しそうに見えます。しかし、黄身色が多少違うからと栄養価に何の変化はありません。この黄身色は鶏の食べる飼料によるものです。この濃淡はとうもろこしや、乾燥アルファルファなどの素材の配合率によって違いが出てきます。食欲のそそる濃い黄色にするために、よく配合されているものは、黄色とうもろこし、アルファルファ、にんじん、パプリカ(トウガラシやピーマンの仲間で現在サラダなどに人気の野菜です)などがあります。また色が濃いから新鮮という捉え方も間違いです。黄身色は鶏の飼料によって左右されるものなのです。
黄身の色が黄色い濃い色だととても美味しそうに見えます。しかし、黄身色が多少違うからと栄養価に何の変化はありません。この黄身色は鶏の食べる飼料によるものです。この濃淡はとうもろこしや、乾燥アルファルファなどの素材の配合率によって違いが出てきます。食欲のそそる濃い黄色にするために、よく配合されているものは、黄色とうもろこし、アルファルファ、にんじん、パプリカ(トウガラシやピーマンの仲間で現在サラダなどに人気の野菜です)などがあります。また色が濃いから新鮮という捉え方も間違いです。黄身色は鶏の飼料によって左右されるものなのです。